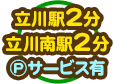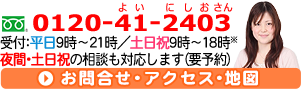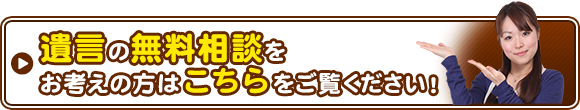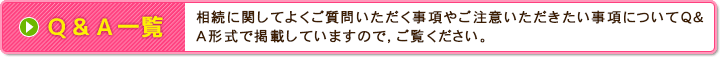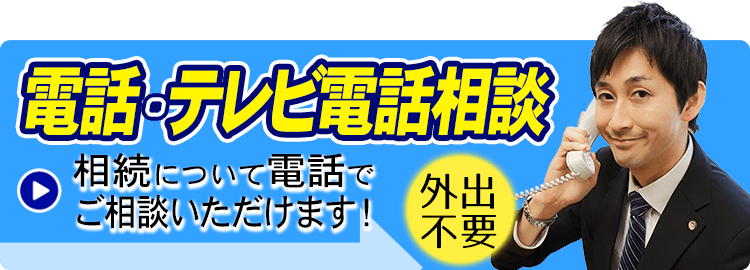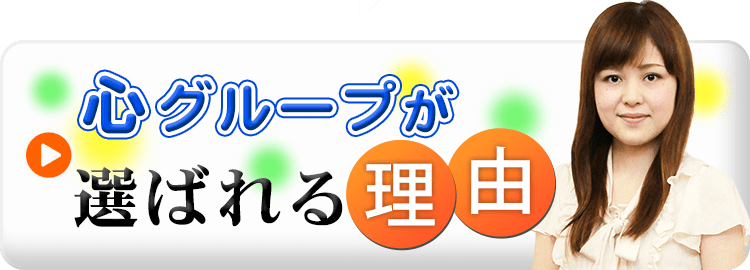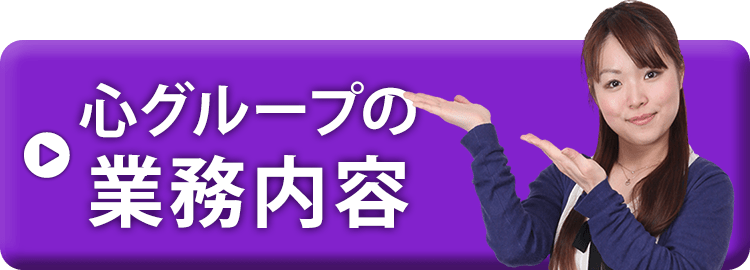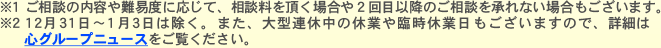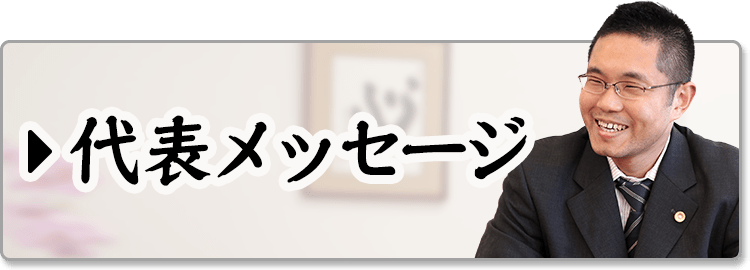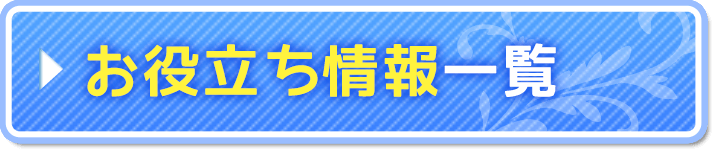遺言書の検認手続きをしないとどうなるのか
1 様々なリスクがある
お亡くなりになられた方の自筆証書遺言書を見つけたものの、自分が想定していた遺言書の内容と少し異なっていることから、検認手続きを行いたくないというご相談は少なくありません。
しかし、自筆証書遺言書の検認手続きを行わないことには様々なリスクがあります。
今回は検認手続きをしない場合のリスクについてご紹介していきます。
2 検認手続きを行わないことによるリスク
検認手続きを行わなかった場合、以下のような不利益を受ける可能性があります。
- ・ 遺言書の効力に従った相続手続きを行えない
- ・ 罰則が科される可能性
- ・ 相続の欠格、受遺能力の喪失の可能性
- ・ 損害賠償請求をされる可能性
⑴ 遺言書の効力に従った相続手続きを行えない
まず、自筆証書遺言書を相続手続きで使用する場合には検認手続きを行わなければなりません(民法1004条1項)。
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
そして、検認手続きを行うと、家庭裁判所から「検認済証明書」を発行してもらうことができます。
参考リンク:裁判所・遺言書の検認
この証明書が添付されている遺言書でないと銀行口座の解約や不動産の名義変更といった相続手続きで使用することができません。
そのため、自筆証書遺言書の場合には、検認手続きを行わないと、相続手続きを進めることができないというデメリットがあります。
⑵ 罰則が科されるおそれがある
自筆証書遺言書を提出しなかった場合などには、5万円以下の過料が科されるおそれがあります(民法1005条)。
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
この「過料」は、行政罰であり、刑事事件の手続きとは異なるため、前科が付いたりすることはありません。
しかし、自筆証書遺言書を提出しないと、このような罰則が科されるおそれがあることは知っておく必要があるといえます。
⑶ 遺言書を故意に隠匿した場合には、相続欠格(民法891条5号)、受遺能力の喪失のリスクがある(965条)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
…
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
相続の欠格は、相続人が遺言書の隠匿等を行ったことにより、当然に相続人となる資格が奪われるとする制度です。
言い換えると、遺言書の隠匿を行った相続人の相続権が無くなってしまうということです。
自筆証書遺言書の存在を知っていたのに、検認手続きを行わない場合、他の相続人から遺言書の隠匿を行ったのではないかと疑われてしまう可能性があります。
相続権が無くなってしまうと、遺産に対する持分等も一切請求することができなくなってしまうので、注意が必要です。
また、相続人ではないものの、遺言書によって遺産の一部または全部を受け取れることとなっていた受遺者についても同様に、受け取る権利が無くなってしまいます。
⑷ 損害賠償請求をされる可能性
検認手続きを行わなかった経緯によっては、不法行為に基づく損害賠償請求を受けてしまう可能性もあります。
例えば、自筆証書遺言書の存在を知っていたのに、自分に不利益であることから、誰にも伝えずに遺産分割手続きを進めてしまったという場合は、最終的に自筆証書遺言書によって財産を受け取れるはずだった相続人等から損害賠償請求をされるかもしれません。
他の相続人からすると、本来自身が受け取れる可能性があった財産を隠匿によって受け取れなかったという状況となるため、損害賠償請求が認められる可能性はあります。
お役立ち情報トップへ 死亡した人の口座から預金を引き出すための手続き