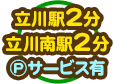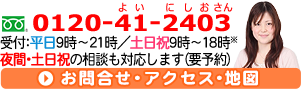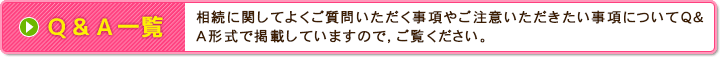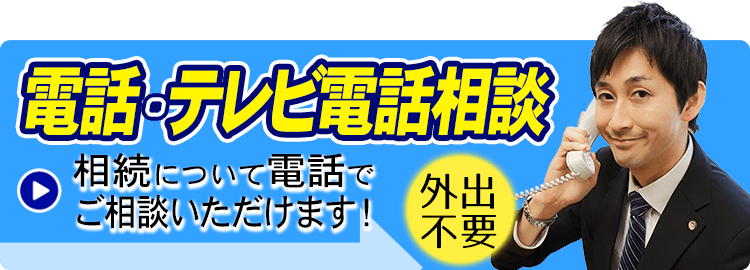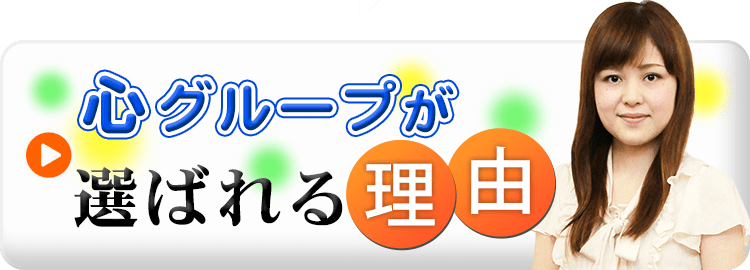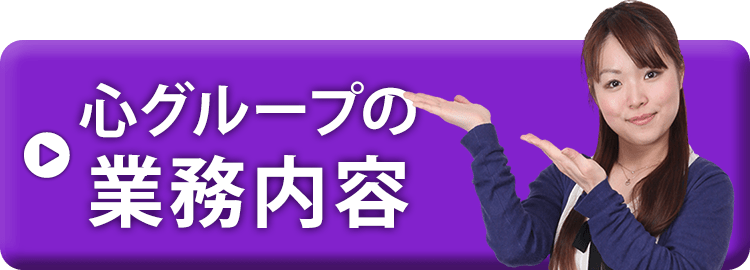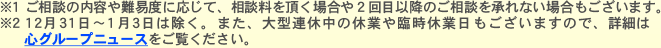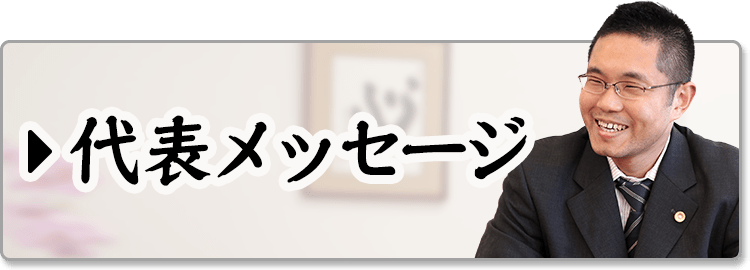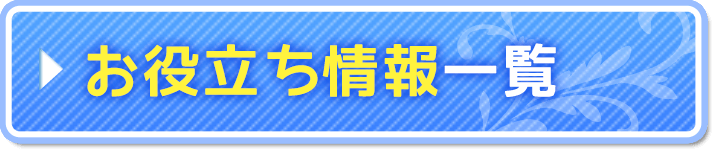相続税の税務調査
1 相続税の税務調査が心配な方へ
相続税の申告で、できれば税務調査を受けたくないと考えるのは皆さん共通です。
調査が入る確率は、続税申告のやり方や生前の準備次第で下げることができます。
また、もし税務調査が入ったとしても、正しく相続税の申告を行っており、税務調査に対しても正しく準備し適切に対応すれば、問題なく終わるはずです。
今回の記事では、相続税の税務調査に焦点をあててご説明します。
2 相続税の税務調査はどのようなものか
⑴ 相続税の税務調査について
相続税は申告納税方式ですので、相続が発生したら自動で計算から納税までされるわけではなく、自分(あるいは依頼する税理士)で税額を計算して申告・納税します。
相続税の税務調査は、この申告・納税された相続税が正しいかを確認するために税務署が行う調査です。
調査の形式としては、追加書類の提出を求められたり、税務署の職員と直接面会して行われます。
⑵ 相続税の税務調査が入るケース
税務署は、その権限から被相続人の財産について様々な情報(金融機関情報、不動産情報、保険会社情報、確定申告・年末調整情報等)を入手することができます。
税務署が入手したこれらの情報と申告内容に齟齬がないかチェックして、申告内容や申告額が間違っている、あるいは故意に納税を免れるためにごまかしている等、疑問点や不審点があると税務調査が入られることとなります。
申告総数の約2割に対して調査が入り、税務調査入った場合は、その8割以上に追徴税のペナルティが発生しているといわれています。
⑶ 相続税の税務調査が入りやすいケース
「申告内容に誤りがある、添付書類の不備がある」といったケースは調査以前の問題ですが、それ以外に税務調査が入りやすいのは次の場合です。
・被相続人に収入が多かった割に相続財産が少ない場合:典型的な税務調査のポイントで、「財産隠し」の可能性が疑われます。
・家族に多くの財産がある場合:相続税対策として生前贈与が行われていた可能性があるため、正しく贈与が行われているか、名義預金ではないか等を確認します。
・相続額が大きい場合:特に2億円以上など、相続財産が大きい場合には、税務調査が入る確率が上がります。
・海外資産がある場合:海外に財産を隠していることが疑われ調査されます。
税理士に依頼せず自分で申告した場合:相続税は相続人本人でも申告できますが、計算が複雑で必要書類も多く、計算間違いや相続財産の見落としなどが起こることが多々あるため、税理士に依頼せず自分で申告した人は、調査されやすい傾向があります。
⑷ 任意調査・強制調査の違い
①任意調査
任意調査は、事前に税務署から税務調査を行う旨の連絡があり、調査日時を決めて行われる調査です。
被相続人が住んでいた自宅で行われることが多いです。
任意調査には、可能であれば相続人全員(全員が無理な場合はなるべく多くの相続人)が出席する必要があります。
また、税理士も立ち会うことができます。
調査では、調査官からの質問に答え、必要に応じて預金通帳や不動産の権利証等の関連書類がチェックされます。
②強制調査
強制調査は、任意調査を拒否したり、明らかに悪質な脱税が疑われたりする場合等に行われる調査です。
事前に連絡はなく、抜き打ちで調査に入ります。
しかし、任意調査を拒否しなければ、強制調査が入るケースはほとんどありません。
3 相続税の税務調査の流れ
⑴ 税務署からの事前連絡
まず、税務署から、相続人あるいは申告を依頼した税理士に税務調査に入る旨の連絡が入ります。
税務署と調整して、調査の日時を決めます。
⑵ 事前準備
税務調査には税理士も立ち会えますので、相続税申告を依頼した税理士に立ち会いを依頼してください。
相続税を自分で申告した場合でも、この時点から税理士に依頼することが可能です。
次に、税理士と協力して必要な相続関係の書類を揃えるとともに、提出した申告書の内容を改めて確認しておくことが大事です。
なお、税務調査の事前に揃えておく主な相続関係の資料には、次のような書類があります。
・相続税申告で使用した資料の原本
・被相続人の預貯金通帳一式
また、相続人の財産についても質問されますので、下記の資料も準備しておきます。
・相続人の預貯金通帳一式
・有価証券残高、不動産権利書等の主要資産の資料
⑶ 調査当日
当日は、相続人全員(全員が無理な場合はなるべく多く)と税理士が出席します。
午前中に調査官による聞き取り調査が行われます。
午後には、預金通帳等の資料の確認、貴重品の保管場所の確認などを行います。
必要な資料を調査官が税務署に持ち帰り、さらに精査を行うこともあります。
⑷ 調査結果の報告
調査官による調査が終了すると、その調査結果が報告されます。
相続税申告の内容に誤りがある場合は、修正申告を行うことになります。
4 相続税の税務調査で聞かれやすい質問
ここでは、税務調査でよく聞かれる質問について見ていきます。
⑴ 被相続人、相続人について
まず、税務調査では、被相続人、相続人について聞かれます。
職業、家族構成、交友関係、趣味、生活等について聞かれ、これらの情報により収入や支出を推測します。
⑵ 被相続人の財産について
本題の被相続人の財産について、聞き取りが行われます。
具体的には、収入や支出、使っていた金融機関、印鑑・通帳等の管理方法などについてです。
特に、現金の動きについては重点的にチェックされます。
被相続人の過去5年分の預金通帳を調べ、被相続人から家族にお金が移されていないかを見極めて、生前贈与や名義預金等がないか探ろうとします。
また、隠し財産がないか、貸金庫の利用については必ず確認されます。
⑶ 相続人や家族の財産について
相続人についても、所有する財産を中心に質問され、被相続人の家族として孫などの財産についても質問されることがあります。
相続人や被相続人の家族が分不相応な財産を持っていないか確認され、持っていた場合は、生前贈与・名義預金等が疑われます。
特に相続人については、取引のある金融機関の口座について過去5年程度の取引内容がチェックされ、生前贈与の有無等がチェックされます。
家族についても、場合によっては相続人と同様に、金融機関の口座情報をチェックされる場合もあります。
5 税務調査で申告漏れが発見された場合のペナルティ
申告漏れが発覚した場合の追徴税には、延滞税・加算税の2つがあります。
参考リンク:国税庁・延滞税について
本来の納付期限を過ぎた後に申告が漏れていた分の税金を納めることとなるため、これらの税金が課せられます。
また、特に悪質な脱税事件の場合は、逮捕・起訴されて裁判によって裁かれます。
この場合は「刑事罰」が課されます。
6 相続税の税務調査を回避するためには
最後に、どうすれば税務調査を受けずに済むか、あるいは税務調査を受ける可能性を低くできるかについて見ていきます。
⑴ 適切に相続税申告を行う
基本ではありますが、正しく相続税を申告することが最も大切なことです。
相続財産の見落としがないように、計算間違いがないように、念には念を入れて確認してください。
⑵ 相続税申告に強い税理士に依頼
相続税の申告は相続人本人でもできますが、相続税申告に強い経験豊富な税理士に依頼した方が税務調査を受ける確率は低くなります。
税理士が行うことにより、申告間違いは少なく、また、税務署からの信頼度はアップするといえるためです。
⑶ 被相続人の財産を適切に把握
相続税の申告漏れは、多くの場合、被相続人の財産の把握に漏れがあるケースです。
最近は、預金通帳のない銀行口座があったりインターネットバンキングを使っていたりと、家族が把握しづらい財産も増えています。
したがって、生前からコミュニケーションをとり、財産全体を家族で共有しておくことが大切です。
⑷ 贈与に関する証拠を残す
ここからは、被相続人が生前にできる対策です。
相続税対策で生前贈与を行うことが多くありますが、贈与を行う場合は、その贈与の証拠を残しておくことが大事です。
贈与は口頭でも成立しますが、税務署に不審に思われないためにも書面で残しておくとよいかと思います。
⑸ 遺言書を遺す
相続財産をどのように分割するか、誰にどの財産を相続させるか等、被相続人と相続人の間でやり取りする場合は口頭で済ませずに文書に残しておくのがよいです。
税務署に対して納税額の正当性をできるとともに、相続人の間のトラブルも事前に防止することができます。
ただし、ただの文書では法的効力がありませんので、遺言書という形がおすすめです。
相続した土地や建物など不動産の名義変更をしないとどうなるか 相続した未利用財産等はどうするべきか